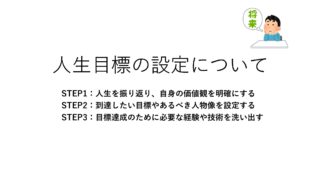プロローグ
「ねぇ、夢はある?」と彼女は言った。
「どうかな、わからない」とぼくは言った。
彼女の髪の毛の色は黒く、肌は雪のように白く、体は鞭のようにすらりとしている。大きな瞳は海のように開き、包み込んでくれる。そんな記憶がある──。かすかに……。
1
この町は狭いけど、美しい。方言のようなものはなくシンプルだけど、多様だ。
ぼくはこの町を愛する。草原と大空に恵まれた夢を見ているように美しいこの場所、人口も少なく住心地も良い。この町の海岸から半島が見える。
ぼくは海岸の一番端に立って、半島を眺めている。あそこには墓があるらしい。噂では探検家の骨がさらされ、大きな熊がうろついているという。島には宝? ぼくのような探険家の心を始終惹きつける秘密が眠っている。
土地はいくつかの秘密を隠し持っているものだ。北国には北国の秘密があり、南国には南国の秘密がある。この町だって同じように秘密がある。
この町の人は夜も戸を締めない。悪いやつなんかいないからだ。もしかするとこの町には神の平和のようなものが広がっているのかもしれない。
この町は何もかもがあの場所とは違う。夜でも明るいのは一緒だけれど、光の発信源が異なる。それが月なのか、街灯なのか。夜に月の光が差している海は上品だけれど、街灯が照らす海は下品だ。住んでいる人はこれを当たり前だと思っているんだろうな。でもぼくは感じているんだ。この月の光が特別なものであることを。
ぼくは静かなところで仕事をしようと思って貯金を切り崩し、この場所にきた。安い賃貸アパートに住んでいる。こちらはデザイナーズマンションです、と説明を受けたけれど、ただ珍しい作りなだけだ。部屋が丸くて、家具は置きづらいし、扉は玄関と浴室とトイレだけ。玄関に入るとキッチンがあり、何の仕切りも無く部屋がある。今は夏だから問題は無いが、冬は玄関から入る冷気で部屋の中は常に寒い。もう住んで三年になる。自分を褒めたい。
2
ある日の午前中に玄関のドアを叩く音がした。すぐにドアを開けた(ぼくはいちいちドアスコープを見ない)。ドアを開けると背の高い男が立っていた。
「同じマンションに住むものですが、これが階段に落ちていたので」と男は言って封筒をぼくの前に出した。
封筒の宛先を見ると、201と書かれてある。それは、ぼくの部屋の番号だった。
「あっ、ありがとうございます」とぼくは言った。
「いえ、では失礼します」と男は階段を上がっていった。
自分ならどうしただろう。ぼくは受け取った茶封筒を持ったまま考えた。もし他人の宛先が書かれた郵便物を拾ったら家に直接届けるだろうか。たぶん届けない。ぼくなら、アパートの入口にあるポストに入れておしまいだ。そうすればいちいち尋ねる必要もない。
そんなことを考えていると上の階で扉の閉まる音がした。さっきの男だろう。冬にはあの男も部屋に入る冷気を嫌うのだろうか。でもあの男にそんな質問をする気にはなれない。
あの男は表情と声が矛盾していた。最初は笑顔で人当たりの良い印象を受けたが、喋りは棒読みだった。しょうがないから持ってきてやったぞ、というような感じ。無理に笑顔を作って話しているのがよくわかった。普段から鍛えているような体格、その幅の広い両肩の上には、哲学者のような頭が乗っていた。量の多い黒髪。鼻は鷲のくちばしのように鋭く、髭は無い。歯は白く光っていた。三十歳位に見えた。
3
ぼくが住んでいるアパートの裏に大きい庭があり、海に接している。ぼくは海岸を沿って歩いていた。波が岸を打っており、波の音が心地よく耳に入ってくる。
ぼくは、海岸から見える小さな丘の上に、小屋を発見した。小屋の右側に木が立っている。
屋根にカラスが止まっていた。
なんとなく怖くなって、小屋を見るのをやめ、ぼくは視線を前に戻した。すると黒猫が海を眺めて座っていた。
「こんにちは」とぼくは黒猫に向かって言った。
黒猫の耳が微動したが、動じる様子は無い。体勢を変えること無く、まっすぐに海を見ている。ぼくは黒猫の右側に座った。ぼくの目線の先は、半島だ。あの島にはいくつもの噂がある。偉い人の墓があるとか、宝が隠されているとか。
「きみはなぜ海を眺めているの?」とぼくは言った。
黒猫は相変わらず海を見ている。堂々とした佇まいを見ると「うだうだ言うな、真っ直ぐ前をみろ」と言っているようだ。
ぼくはまた視線を戻し、半島を眺めた。
「夢はある?」
あのとき彼女は言っていた。あのとき、と言っても、いつなのかは覚えていない。でも彼女の表情は覚えている。
大人になったぼくは夢について考えることは無くなった。朝早く起きて、髭を剃り、髪をセットして朝ごはんを食べずに家を出る。不幸せそうな表情を浮かべた乗客と共に満員電車に乗り、会社に出勤しては、上司の顔色を伺いながら仕事をして、仕事が終わったら酒を飲む。そして次の日の朝が来る。毎日同じことの繰り返しだ。そんな世界に住んでいたぼくは、夢を考えている余裕なんてものは無かった。でもこの町にきてからは、よく考える。この町の時間の流れは遅く、ぼくに余裕を与えてくれる。今のぼくなら彼女にこう返事をするだろう。
「夢か、いまは余裕があるから、じっくり考えてみるよ」
彼女はなんと言うだろうか。「いちいち考えないとわからないの?」とぼくの目を見て言うだろう。
「じゃあまたね」
ぼくは隣に座っていた黒猫に言った。黒猫は無視した。
4
ある夏の日、この町に台風が直撃した。風が強くて窓が割れるかと思うほどだった。もちろんぼくは家に居た。
台風が過ぎ去ったあと、いつもの海岸に行った。ぼくは丘のほうを見た。丘の上の小屋も、生えていた木も一応は大丈夫だったみたいだが、木の枝が全体的に左に寄っている。まるで木が小屋を守るように。
木は強風に耐え、自分の足で立っているのだ。称賛に値する。
ただ同時に、可哀想な気持ちにもなる。木はその場所から動くことができない。その場所でどう生きるかが、木の課題なのだ。
今日も黒猫は海を眺めていた。
「また会ったね」とぼくは言って、黒猫の隣に腰をおろした。
相変わらず黒猫は前を見つめている。目線の先は海だ。
「夢はある?」とぼくは言った。
黒猫は大きなあくびをした。「そんなことを考えて何になる?」と言っているようだった。
台風が過ぎ去ったあとの空は、深い青でぼくたちを迎えてくれた。波は穏やかで、海風がほどよくやってくる。ぼくは両手を空に上げて背伸びをした。自然と大きなあくびが出た。
「仕事を辞めてよかったよ」とぼくは黒猫に話しかけるように言った。
「あのころは毎日同じことの繰り返し、詳細に見れば、毎日違うことをやっているけれど、大体は同じことだ。朝起きて、満員電車に乗って会社に行く。仕事が終われば酒を飲み、家に帰って寝たら、また朝が来る。どう思う?」
黒猫は黙っていた。
「朝が来ることは悪いことじゃ無いんだけどね」とぼくは言った。
波の音がゆっくりと耳に入ってくる。これが続けばいいのにな、と思う。
「仕事をやめてから気づいたんだ。世界はこんなにゆっくりと動いているんだってね。忙しいのは人間だけだよ。人間は飽きもせずにどんどん新しい価値を生み出している。やることが増えていくんだ。その代わりに時間が無くなっていく。それがイノベーションってやつさ」
しばらく黙っていると、黒猫はぼくを向いた。眠そうな顔をしていた。
「きみは何を考えているの?」とぼくは言った。
黒猫はぼくを無視して、また海の方を向いた。
「また来るね」とぼくは言ってアパートに戻ることにした。
アパートの入り口に近づいたとき、この前の男が反対の道から歩いているのが見えた。ぼくは少し迷ったが、この前のお礼を言うことにした。
「こんにちは。この前はありがとうございました」とぼくは男に言った。
男は困ったような顔でぼくを見た。覚えていないのだろうか、突然話しかけられて動揺した様子だった。
「あの、郵便物を届けていただいて……」とぼくは言った。
「あー、いえいえ。とんでもないです。ただ届けただけですから」と男は言った。相変わらず、その言葉に感情は無かった。
そしてぼくが先にアパートに入り、201号室に入った。その数秒後、ひとつ上の階でドアの閉まる音がした。
ぼくはクーラーをつけ、珈琲を淹れた。そして分厚い本を本棚から取り出した。それから九時間後に眠りについた。
5
夏の生活。明るい色の服、麦わら帽子、はしゃぐ子どもたちの声、スカートから出る魅力的な脚。それらはたちまちにひらめき去って、夢のごとく消えていく。道の上を秋の風が威風堂々と立ち、散った花や落ち葉が踊っている。
葉が赤く染まった頃、ぼくは日記をつけ始めた。その日になにをしたのか、そして余裕があれば、そのときになにを感じたのかを記録した。書くのは一日の終わりだ。ぼくは寝るのが遅かったから大体は夜中の二時ごろに書いた。
日記帳は、本屋で偶然見つけた。その他の文庫本と一緒に陳列されており、ただの文庫本にしか見えなかったが、開くと日付入りのノートだった。その日から、日記帳を持ち歩いている。解約したスマートフォンの代わりにふと、自分が書いた日記をみる。はたから見ると本を読んでいるようにしか見えない。誰も自分が書いた日記を読み返しているなんて思わないだろう。振り返ることは今の時代にあっていないからだ。いまは、最新の情報を正確に処理して、未来に活かすことが求められている。日記を書いている人は少数だし、そのなかでも読み返す人はごく一部だ。 もしかすると世界でぼくだけかもしれない。
ぼくはいつものように海岸にやってきた。海風が冷たい。黒猫の姿は無かった。寒くなってから見なくなった。どこか別の暖かいところにいるのだろう。海風は容赦なくぼくの身体を冷やした。日記帳を取り出し、今日のページを開いた。「海岸、寒い、風」と鉛筆で薄くメモをした。このメモはあとで消しゴムで消す。あくまでも日記の書き出しをスムーズにするためのものだ。寝る前に日記帳を開き、その日の出来事を書こうとしてもすぐには思いつかないことだってある。でも、とっかかりさえ思い出せば、記憶は連鎖的に表面に出現する。
ぼくは思い出す。子供のころの記憶はふと、なにかをきっかけにして思い起こされる。耳にする音、目にしたもの、漂ってくる匂い、要するに五感を通じて、突発的に湧き出てくる。それが自分にとって良い記憶なのか、悪い記憶なのかは関係が無い。でも思い出されると懐かしい気持ちになり、時の流れの速さと、過ぎてしまった過去に戻りたい気持ちを彷彿とさせる。過去は戻ってこないし、未来は着々と現在の結果を組み立て、作り出されている。
6
ある日、ぼくは本棚から小説を手に取った。それは五感を通じて思い出された一冊だった。この物語の主人公は“タイムトラベラー”で、タイムマシンを発明した男だ。
タイムトラベラーは知人を自宅に集め、発明したタイムマシンの原理を説明した。しかし説明を受けた知人たちは何も信じなかった。説明だけでなく、タイムマシンのレプリカを使って、その事象を目の当たりにしても「それは手品かい?」と言うだけだった。それでもタイムトラベラーはタイムマシンを使って未来の世界に向かった。タイムマシンは、八十万年後の世界に到着した。未来の人間に教養は無く、文字も読めなかった。知識は明らかに衰退していた。人間の格差は大きくなり、明るい場所にいる人間と暗い場所にいる人間とを明確に区別していた。一方は知識は無いが幸せに、一方は人間とはかけ離れた動物のような生活を送っていた。
この世界では、テクノロジーが頂点に到達し、人間は何もしなくても生活できるようになった。その結果、人間は学ぶことをやめ、知識は失われてしまった。それは起こり得る現実であると思った。でも世界は全く変わること無く、新しいテクノロジーを生み出そうとしている。物語は人の行動を変えることはできないのだろうか。進歩とはなにを指すのだろうか。
7
「暖かい部屋でしょ? 色んな意味で」と彼女は言った。
「うん。この暖炉も部屋の色も暖かい」とぼくは言った。
「ここでよく考え事をするの」
「なにを考えるの?」
「それは教えられない」
「なんで?」
「だから教えないって」
一体、彼女はなにを考えていたのだろう。ぼくはあのとき子供なりに考えた。でも当時のぼくはなにも思いつかなかった。
そんなぼくは、なにも考えずに、ある程度定められたルートを辿って社会に出た。多くの人間がそうしているように。でもそれはとてもつまらないことだった。世界には色んな人がいて、色んな考え方があった。好きな食べ物、好きな色、好きになる女性のタイプだって違うんだ。なら生き方にもいろんなタイプがあってしかるべきでは無いか。大人になったぼくはそう考えるようになった。その考えが現在の生活に繋がっている。例えば、海岸に行って黒猫に話かけることだってぼくにとっては重要なことだ。静かにゆっくりと自分の生を過ごす。毎日ゆっくりと思考を巡らせて、曖昧なことを感じては、また思考を巡らせる。時には行動だって起こす。そうやって生きていく。
エピローグ
「ねぇ、夢はある?」と彼女は言った。
「考えはあるよ」とぼくは言った。
美しい彼女の耳が、続きの言葉を待っていた。